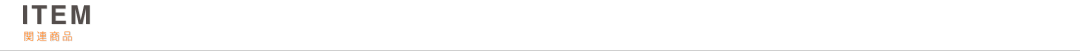女性の告発に、なぜ目をつぶるのか
昨今、話題のニュースで最も気になったのは、実の娘に対する強姦罪で、犯した父親が無罪と判決された事犯。母親含む兄弟5人も同居している家庭で、12歳の娘が夜毎父親に陵辱されながら誰も助けられなかった。無罪となった理由は、裁判所がこの娘の同意はなかったこと、精神的に支配されていた状態だったことを認めるも、“拒めないほどの暴力”は受けていないと判断したから。
この判決については、納得できない人々の怒りが爆発しているようだが、それにしても、家庭内で秘められてきた性暴力がここまで正々堂々と「加害者の無罪」と判決が下ったことには、驚かされる。娘の同意があった、と主張する父親は、未成年の娘に対し、魂の殺人を犯したという意識はないようだ。何より、罪の判定を下す裁判官までもが、モラルをはずした決着をつけた。
一方、未成年で被害を受け、裁判で負けた娘は、さらに重い未来を背負うことになる。性暴力は、加害者が父親である時点で同意云々を問うことも、もはや論外と思われる。性的処理のために娘を生んだとしか思えない父親の行動は、他人が行なうのと比較できないほど、罪深い。
しかし、親子という関係上、最も訴えにくい状況で、家族全体のデメリットや親から得たい愛情の気持ちも複雑にからまって、犠牲の道を選ばざるをえないと我慢した娘の被害は計り知れない。
抵抗できない娘を性処理の道具とした時点で、父親には、情状酌量の余地はなく、“鬼畜”の烙印を押されるべきだろう。法律の文字面を追って、裁判の判決にいたる裁判官の情緒的育成は、必須だ。こうした性暴力については、被害者の感情を理解する、想像力を養う方法として、映画が有効な教科書となるだろう。
ハリウッドアクター、「海の上のピアニスト」主演のティム・ロビンスが初監督した「素肌の涙」(1998年、英国)は、実の父親による性的虐待をテーマに、強烈な印象を残した。

「素肌の涙」(1998年、英国)

舞台は、田舎の牧歌的な風景の中で、二人の姉弟と夫婦が4人で暮らす、ごく普通の家庭。小太りの落ち着いた体格の父親を中心に、母親が3番目の子供を孕み、いかにも幸せそうな顔をしている。しかし、そこには隠された家族の秘密があった。
ゆるみかかった母親の肉体を、舐めるようにして撮影するシーンが意味深い。妻が母として変わりゆく中で、女性の肉体を魅力的に見せるのは、若い娘に違いない。
ある日、外から帰った弟が、姉と父親が風呂場にいたことで、妙な違和感を覚える、というところから物語は展開する。弟は、何かおかしなものを感じて姉に詰め寄るが、姉は何も語らない。弟の疑いの目は、それから姉と父親の様子に集中する。そしてついに、姉が不在のとき、急に出かける父親の後を追うのだが……。家から離れた小屋のなかを覗いた弟は、そこで姉と父親の信じられない光景を目の当たりにする。
本作は、ある物語を役者の魅力や脚本の面白さで見せるといった、ドラマチックな構成ではない。近親相姦のテーマを正面に見据え、ジャーナリスティックな視点で描かれた問題意識の強い演出である。そこを感じられるかどうかで、映画の見方が問われるはずだ。
小屋の中で営まれる父親と娘のシーンは実に淡々とし、暴力を振るわれて口をふさがれたり、騒いだりしているわけではない。求めに応じた娘の哀しみにあふれる表情が静かにクローズアップされ、なんとも切ない。助けを求めるすべがない不条理の涙を落としている。
いつのまにか父親の誘導でパターン化され、合図とともに小屋に行く娘の辛さ、抵抗できない状況を女性なら誰しも察することができるだろう。
小太りのおやじが、なぜ、父親らしい愛情で、普通に娘を愛せないのか?なぜ彼女は、生みの親に日常的な性の対象にされなければならなかったのか?
彼女は、若い肉体を持つ、というだけで、いかなる罪深さを持つのか?弟や母親に言えない感情、同意の可能性を疑われてしかるべき無抵抗……本作を見れば、曖昧な女性の行動の中にある、心の闇、深い絶望感を感じるはずである。仮に、大声を上げて抵抗しない娘を見て、父親との性行為を楽しんでいると解釈できる男性がいたなら、病院に行ったほうがいい。
本作を、互いの愛情や肉欲から発した近親相姦物語として解説する記述も一部ネット上で見かけられたが、それはまったくの間違いだ。タイトルにあるように、素肌を見せる少女の「涙」にあふれた物語で、彼女の魂の叫びが描かれている。
それにしても、名優、ティム・ロビンスがなぜ、こんな衝撃的な題材を初の監督作に選んだのか。監督としての視点は、性的被害を受けた者の怒り、嘆き、叫びが伝わるものだった。レイプ、性的虐待を受けた女性の気持ちをここまで汲むことができる男性は、そうそういるものではない。
かくして、その理由がのちにわかった。ティム・ロンビンスもまた、身内から性的虐待を受けていたのだ。幼い頃に受けた“祖父”からの性的虐待をカミングアウトした。なんと、彼の父親もまた、同じ人物(父親の父親=ティムの祖父)から性的虐待を受けていたというのだ。同性からの性虐待は、異性間より軽いとか、重いとか、そんな問題ではない。親が、性のはけ口に娘や息子、孫を対象にするとは、どういうことなのか?
身内から、性的な対象物としてではなく、人間として愛されたいと願うのは当たり前の願望で、歪んだ性愛のえじきにされたくないのは誰もが望むところ。まっとうな愛情の環境を作るのは親の責務であり、歪んだ愛しか与えられない親は、もはや子どもを持つ資格はない。
父親による性的虐待といえば、内田春菊原作の「ファーザーファッカー」(1993年、日)は、作家本人の自伝。ただ、彼女の場合は、加害者が養父である。問題ある家庭環境のなか、母親が家に連れ込んだ養父から精神的支配を受け、ついには性的被害に及ぶ。母親が知っても、娘をさしだすことしか、逃げ道がない。支配的な立場を手にした男は、やり放題なのだ。誰もが倒せない養父のいる環境の中で、未成年であるヒロインは後先を考えず、家から逃げ出す。水商売を転々としながら、作家としての才能にたどりつく人生は、力強い。ヒロインは逆境により、成功した女性といえるが、だからといって、この養父が罰を受けなくてよい理由にはならないだろう……。
「ファーザーファッカー」は、実に良いタイトルだ。“マザーファッカー”は、ママとやってなさい、という侮辱的な意味で男子を揶揄する表現だ。ママと性的関係を持つというタブーを示しているが、ジョークでも、女子いじめに“ファーザーファッカー”とは言わない。シャレにならない重さを感じさせるからだろう。
養父から性的虐待される娘といえば、「ミレニアム ドラゴンタトゥーの女」(2009年、スペイン)シリーズのヒロイン、リスベットも同じ経験の持ち主。本作はレイプをテーマとする作品ではないが、強烈な個性の調査員、リスベットの生い立ちが、幼い頃の悲惨なDV環境と、後見人による性的虐待だとわかる。そうした男たちへの復讐シーンは、残酷なまでに躊躇のないやり方で、痛快そのもの。このタフなヒロイン像には、多くの女性の心が救われた。
もちろん親でなくとも、女性をレイプする男は、“鬼畜”と言っても言い過ぎではない。ただ、証拠が明確に出せない場合、女性の主張だけでは信じてもらえず、女性に落ち度はないのかという男性的な偏見が加えられた捜査、裁判があるため、訴えることを断念しがちである。セカンドレイプと呼ばれる状況を、映画は何度も描いてきた。
1970年代は、アメリカでレイプが社会問題化していた。そんな中、マーゴ・ヘミングウェイ主演の「リップスティック」(1976,米)はレイプの裁判シーンを中心とする映画で、大ヒットした。一見まじめな音楽教師が、主人公のモデルをレイプするも、巧みな公判戦術で無罪になる展開。レイプ裁判という戦場は、まさに男のものと言えるのか。やがて、この教師から、なんと未成年の妹までレイプされたことから、主人公は正気を失う。狩猟用の散弾銃をかまえて、ズドドドド、と撃ちまくるシーンはかなりの迫力で、スーパーモデル、マーゴのこれでもかという撃ち方に鬼気迫るものがあり、女性の気持ちを代弁した。ちまちま探る裁判なんかあてにならない、くそくらえ、という命がけの怒りが伝わる映画らしい映画である。
その後日本でも、ジェンダーをテーマにした作家、落合恵子がレイプ小説を書いたものが映画化された。落合恵子は、田嶋陽子や上野千鶴子といったフェミニズム闘志の先人であり、自らオーナーとなるクレヨンハウスでは、幼少の頃から男女差別の意識をなくそうと考えた児童書を揃えた、筋金入り。
この落合恵子原作の映画「ザ・レイプ」(1982年、日)では、顔見知りの男に突然レイプされ、「合意だった」と男に主張されたことから、レイプ裁判の厚い壁にぶつかっていく主人公の苦悩が描かれる。裁判に立ち向かう中で、取り調べのやり方は、さらなる精神的レイプになる。やがて彼女をサポートする恋人さえ、挫折しそうになり、二人の関係も難しくなっていく。それでも、ヒロインは立ち向かうのだが……。日本で社会派のレイプ映画が大ヒット、という方向にはいかないようだが、B級路線に潜り込ませたような状態で公開され、田中裕子の魅力もあって話題となった。
一方、ジョディ・フォスター主演の映画「告発の行方」(1988年、米)は、酒を飲み、マリファナを吸っていたハスッパなヒロインが、ピンボール台の上で見知らぬ3人の男たちにレイプされ、女性弁護士とともに裁判で戦う物語。
女性が嫌がるとき男たちは、いつも「合意」と言えばすむと思っている。むらむらときて、強引に迫り、無理やり行なっても、「合意」と思いたいのが男性の心理だろう。しかも、女はだらしなく、遊んでいるようなタイプである。しかし日本と違い、アメリカではこんなすきだらけの、底辺の状況で生きる女性だからこそ助けようとする。
酒場にいた女⇒「男にだらしなく、あなたにもすきがあったのではないか?」
こうした偏見を突破しようと、女性たちがスクラムを組む。エリート弁護士の女性が、弱い立場の女性を助けるべきであることを本作では、強く訴えるのだ。エネルギッシュな正義感を持つ弁護士役のケリー・マクギリス(「トップガン」のヒロイン役)は、実際にもレイプされた経験があった。
それにしても、自分がレイプしたことがあるわけでもないのに、なぜ男性捜査官は、被害女性にセカンドレイプのような扱いをするのだろうか?なぜ、加害者より被害者に対して、攻めるような姿勢になるのであろうか?捜査官に限らず、一般的にも、レイプは、被害者に対する偏見を持つ人も少なくないのはなぜなのだろうか?
いずれにしても、大きな抵抗を見せない被害者については、「素肌の涙」にあるように、性的虐待が常習性のある行為となれば、そこに黙って身を置くのは適合する自分を作り、なんとか生き残るための手段を見つける行為である。決して喜んで受け入れた状況ではないことを知るべきだ。
最後に、男が男をレイプする「スリーパーズ」(1996,米)は、少年院でレイプされた少年たちが成長し、検事やジャーナリストになってから、完全復讐に向かう物語。男たちが、レイプの怒りを体感するとしたら、むしろ男の被害者状態を見るべきかもしれない。舞台が少年院だけあって、レイプシーンの恐ろしさは十二分に伝わる。
裁判官に限らず、男性一般には、こうした映画による体感教育をしてもらいたい。
N A H O K Information

木村奈保子さんがプロデュースする“NAHOK”は、欧州製特殊ファブリックによる「防水」「温度調整」「衝撃吸収」機能の楽器ケースで、世界第一線の演奏家から愛好家まで広く愛用されています。http://nahok.com
NEW PRODUCTS
Wケース 2コンパート・リュック ‘‘Carlito’’ (カリート)3色、完成。オーボエ、クラリネット、フルート対応で、近々に発売予定!!
Wケースと面は同じサイズで2コンパートメントです。ケースと別に小物が入り、本格的な止水ファスナーの リュック使用です。
製品の特性:ドイツ製完全防水生地&湿度温度調整素材 with 止水ファスナー
生産国:Made in Japan / Fabric from Germany
問合せ&詳細はNAHOK公式サイトへ
>>BACK NUMBER
第1回:平昌オリンピックと音楽
第2回:MeTooの土壌、日本では?
第3回:エリック・クラプトン~サウンドとからむ生きざまの物語~
第4回:津軽のカマリ、名匠高橋竹山の物語
第5回:ヒロイックな女たち
第6回:アカデミー賞2019年は、マイノリティーの人権運動と音楽パワー
第7回:知るべきすべては音楽の中に――楽器を通して自分を表現する
第8回:看板ではなく感性で聴くことから文化が高まる