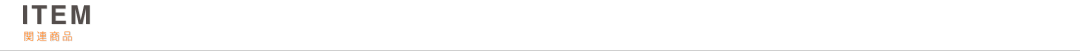フィル・ウッズ 追悼
SAX ONLINE SPECIAL

チャーリー・パーカーの流れを汲むアルトの最高峰、フィル・ウッズが、2015年9月29日、肺気腫の合併症のため米東部ペンシルベニア州で亡くなりました。享年83歳。
フィル・ウッズは、1931年11月2日米国マサチューセッツ州スプリングフィールド生まれ。12歳で初めてサックスを手にし、ハービー・ラローズに師事。その後、ベニー・カーター、チャーリー・パーカーに影響を受けニューヨークに渡りました。マンハッタン音楽学校、ジュリアード音楽院で学びながら、レニー・トリスターノに師事。1968年には、フランスに移り当時の欧州で最強のピアノ・トリオとヨーロピアン・リズムマシーンを結成、ハードバップで自己のスタイルを確立しました。1973年アメリカに戻り、自己のクインテットを中心に活動。また、ジャズだけに留まらず、数々のシーンで活躍しました。ビリー・ジョエルの名曲『素顔のままで』のサックスソロ名演は誰もが耳にしたことがあるでしょう。自らの音を通して人々に音楽の素晴らしさと感動を与え続けました。心より、ご冥福をお祈りいたします。
フィル・ウッズ氏に追悼の意を込めて、これまでのTHE SAX インタビュー記事の中から心に響くメッセージを抜粋して紹介いたします。
音楽には人の生き方を変えるような強い力がある
「ジャズは言葉に置き換えることが難しいほどの深い意味合いをもっているし、とても強い力をもっているんだ。人の心に触れることの大事さを満たしていると思う。その人の音楽にハートがあり、知的で真摯な心であれば、国や言語に関係なく誰にでも届くものだよ」
うまくなるための近道はない
「うまくなるためには、“練習すること”としか言えないな。やはり近道はないね。“10%の才能と90%の努力”というように、小さな種でも大きくきれいな木に育つように、自分に授かった才能を育てるのは自分なわけだ。」
美しい音を出すためには
「それには特にロングトーンの音色を練習することだ。たった一つの音で人の心に触れ、感動を与えることができるんだよ。速いパッセージや短い音を演奏するのは練習すればだれにもできることだが、シンプルな音をはっきりときれいに演奏し、人を感動させるのはとても難しい。特に年をとると、とてもエネルギーを必要とする。私はメロディをできるだけきれいに演奏することを愛しているんだ。」
輝きのある音色と、豊かな響き
「自分の体の幹、中心を感じてそこからエネルギーを出さなければいけない。体を大きく動かすのは要注意だね。指使いもそうだ。”常にパール(貝)を感じろ” そう私は習った。うまい人になればなるほど全く動いていないように演奏するだろう?ピアノや他の楽器でもそうだ。指がキィに近ければ、それだけすばやく動けるから最低限のエネルギーで済む。気と心、考えることに集中して、そこにエネルギーを使うんだ。」
チャーリー・パーカーの演奏が真に求めるべきものを気付かせてくれた
「あるクラブでアルバイトをしていた時、チャーリー・パーカーが近くで演奏していると聞いて駆けつけた。彼は低音を気持ちよく演奏していないように見えたので、私のアルトを使ってみますか?と聞いてみたんだ。それは助かる、と言って彼は私のアルトを吹き始めた。それはもうすばらしく吹くのさ!この瞬間、私の楽器に悪いところはない、何が正しいか気づかされた。」
「私はいつも心を表現したいと思っている。そう、サックスを吹いていないときだって、常に思考することが大事だ。学生のころはいつも頭の中で練習していたよ。頭の中でいつも歌を歌っていたし、コードを覚えた。寝る前にも頭でエチュードの練習をしていたな。一日の終わりにその日の内容を復習して、次の日の朝ちゃんと頭の中に残っていて、そこからまた始められるようにね。」
「私はいつも心を表現したいと思っている。そう、サックスを吹いていないときだって、常に思考することが大事だ。学生のころはいつも頭の中で練習していたよ。頭の中でいつも歌を歌っていたし、コードを覚えた。寝る前にも頭でエチュードの練習をしていたな。一日の終わりにその日の内容を復習して、次の日の朝ちゃんと頭の中に残っていて、そこからまた始められるようにね。」
ビリー・ジョエルの名曲『素顔のままで』でプレイしたいきさつ
「あの曲のプロデューサーだったフィル・ラモーンとは、ジュリアード時代からの友だちなんだ。彼がレコード業界に入ってエンジニアからプロデューサーになって、色々なアーティストと仕事をするようになり、何回か僕のことを呼んでくれてね。そのうちの一つが、あのビリーの曲だというわけさ。」
ジャズの知識が半端じゃない日本のオーディエンス気質
「日本のファンはとても熱心に聴いてくれるし、何よりもジャズに対しての知識が半端じゃない。日本中がジャズの評論家か、とさえ思うほどなんだよ。僕たちが自分たちでも思うほどに良い演奏ができた時には実に熱狂的に拍手をくれるし、逆に今日はイマイチだなと思った際には、拍手が薄かったりする。そういう意味では怖い聴衆でもあるんだけどね。そんな時でさえ、僕たちの体調を気遣うような言葉を掛けてくれたりもするんだ。そんなファンは世界のどこを探してもいないよ。」

【関連雑誌・キーワード・アーティスト】