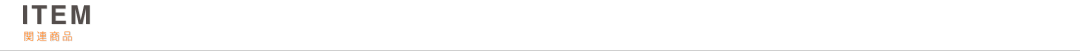恩師リー・コニッツへ捧ぐ鎮魂歌
モダンジャズ全盛期から長きに渡り、インスピレーション溢れる鋭いプレイを信条としたリー・コニッツが、去る4月15日、新型コロナウイルスが原因でこの世を去った。 即興を突き詰めるかのようなコニッツの演奏は、スタイルこそまったく異なるもののチャーリー・パーカーと双璧をなす存在であった。そんな「アルト最後の巨匠」コニッツにアメリカでの演奏時代に師事し、共演も果たした大森明さんに、コニッツとの思い出や音楽について語ってもらった。
コニッツの「超自然体な演奏姿勢」に惹かれて


Photo by Yuki Tei
次ページにインタビュー続く
・「何も思い浮かばなかったら音を出さなくてもいい」
・ ミンガス相手でも自分を曲げない
・リー・コニッツという大きな存在

大森明
Akira Omori
1949年生まれ、福岡県出身。高校時代よりプロ活動を開始。その後、国立音楽大学、バークリー音楽院に学び、在学中からソロイストとして活躍。卒業後8年間のニューヨーク滞在中チャーリー・ミンガスのレコーディング「Me Myself An Eye」「Somethin’ Like A Bird」に参加。1979年、1982年のニューポートジャズフェスティバルへの出演を初め、数多くのミュージシャンとの共演を通して本格派ジャズメンとしてのスピリットを学ぶ。83年バリー・ハリス、ロン・カーター、リロイ・ウイリアムスをバックに初リーダー作「To Be Young And Foolish」を発表。84年帰国後「Back To The Wood」ではレイ・ブライアントを、「Trust In Blue」では、エルヴィン・ジョーンズをフィーチャー、2001年発表の中牟礼貞則氏をフィーチャーした「PRIMEMOMENTS」は「スイングジャーナル」誌のジャズディスク大賞にノミネートされる等、専門家筋の間でも高い評価を受けている。2006年、New York 録音作「Recurrence」、2009年、前田憲男氏との「Matin’ Time」、2015年、Hod O’Brien との「ManhattanSuite」と、常にハイクオリティーなストレートJazz を追求し続ける。教則本の制作も手がけ2005年、新刊著書「実践、Jazz Adlibシリーズ」が出版され、現在もThe Sax誌に自己の連載コーナーを持ち若手の育成にも力を注いでいる。