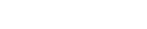03|ウィーンフィル首席奏者から学んだ音楽
音楽家としての基礎を手に入れた内容の濃いレッスンについて
What's えびちゃん留学記 ...
自分が感じる「違い」はなんなのだろう───
演奏の違いから様々なことを探求して行った留学時代と海外生活時代を振り返りながら、現地の情報もお届けします。ファゴット奏者で、指揮、講演、コンサートの企画、オーガナイズ、コンサルティング、アドバイザーなど様々な活動をする基盤となった海外留学とはどんなものだったのか。思い出すままに書いていきます。
Text by ...

蛯澤 亮
Ryo Ebisawa
茨城県笠間市出身。笠間小学校にてコルネットを始め、笠間中学校でトランペット、下妻第一高等学校でファゴットを始める。国立音楽大学卒業。ウィーン音楽院私立大学修士課程を最優秀の成績で修了。バーゼル音楽大学研究科修了。 ザルツブルク音楽祭、アッターガウ音楽祭、草津音楽祭などに出演。元・ニューヨーク・シェンユン交響楽団首席奏者。茨城芸術文化振興財団登録アーティスト。ファゴットを馬込勇、ミヒャエル・ヴェルバ、セルジオ・アッツォリーニの各氏に師事。 「おしゃふぁご 〜蛯澤亮のおしゃべりファゴット」を各地で開催、クラシック音楽バー銀座アンクにて毎月第四金曜に定期演奏、池袋オペラハウスにて主宰公演「ハルモニームジーク 」を毎月第二水曜日に開催するなど演奏だけに留まらず、様々なコンサートを企画、構成している。
巨匠から学んだこと
大学の入試は6月なので、それまではドイツ語学校とレッスンの日々。ヴェルバのレッスンは週2回、火曜と木曜だった。週2回のレッスンは結構ハードだ。毎回エチュードをしっかりした状態で持っていかなければいけないし、ソロの曲も必要だ。入試には数曲必要なので、それらを順番にやっていく形をとっていた。
入試前のレッスンでヴェルバに言われたのは「とにかくドイツ語で話す」ということ。わからない言葉はドイツ語で説明する、それでもわからなければ辞書で調べるということになった。その国の言葉を理解し、発音を学ぶことは音楽や演奏スタイルを感覚的にも学ぶことができるのだと考えていた私と同じく、彼も「ドイツ語が話せないと勉強にならない」と考えていた。意思疎通はもちろん、それが音楽にも繋がると言っていた。そして、直近で必要なのは入試のためだ。ヴェルバが一番心配していたのは入試のドイツ語だった。現在ではドイツ語検定を受けることが義務付けられていたりするが、当時はそこまで厳しくはなかった。大学毎に決められた試験を受けるのだが、問題は面接だ。そこで落とされるのがヴェルバも私も一番心配だった。そのためにも早くドイツ語に慣れるためのヴェルバの気遣いだった。
実はウィーンという街はドイツ語が意外に聞こえないのだ。観光客が多いのはもちろんだが、私が留学した2005年当時もすでに移民が多かった。そんな状況なので中心街のお店へ行っても英語で話かけられていた。しかし、これが不思議なもので数年住むと英語で話しかけられなくなってくる。会った瞬間、私にドイツ語で挨拶してくるようになる。彼らにはそこの住人かどうかを見分ける何かがあるようだ。
肝心の演奏に関しては、「表現が多いのは良いが質が一定ではない」ということを言われた。そのためにも三つのテーマに沿って基礎から鍛えなおすという。
アーティキュレーション
まずはアーティキュレーション。スラーがどこに付いていて、どのような音形によって音の長さや表情、流れを作るかという基礎的演奏法だ。これは初級のエチュード(Satzenhoffer)からアーティキュレーションを細かく学んでいった。既に上級エチュードをやっていたので初級と上級のエチュードをレッスンしてもらうという不思議な感じだったが、昔に学んだことの確認だけでなく、新たな発見もあり、とても有意義だった。楽譜にかかれている内容をクリエイティブに演奏するためには基礎が大事ということは、この後もウィーンで感じることとなる。そこに書かれている音符を生きた音にするためには体系的に楽譜を読む勉強が大事なのだ。
(※下記の参考動画は初歩的なアーティキュレーションの演奏法について解説。)
(URL :https://youtu.be/LkmX6JA9uX0)
息の使い方
基礎のもう一つは息の支えだ。息は腹筋で押すな、腹は息を入れたらしっかりとその容量を保って息を吐けということ。要は外側の筋肉で息を押し込むのではなくインナーマッスルで持続して支えを作る。これが慣れていないうちはなかなかできなかった。
息を吐けば自然とお腹はへっこむ。しかし、なるべくそれをへっこませずに持続することによって安定した豊かな音を出すことができるというのだ。
(URL :https://youtu.be/Z2TpOY2-JPc)
息でいえばもう一つ、不可解な指導があった。息は吐くのではなく、自分の内側に入れるイメージだということ。そこから響きを作っていく音作りが、響く会場でもうるさくなく心地よく聞こえるのだ。
息は吐く。それ自体の行為は変わらないのだがそのイメージの問題だ。ヴェルバは音の後押しをとにかく嫌がる。それはウィーンフィルの本拠地ムジークフェラインやカトリック教会、宮殿のザールなど、天井が高く響きが多い演奏会場が多いウィーンでは、少し音を後押しするだけで、例えどんなに良い発音で美音を出したとしても余計な余韻が増えてごちゃごちゃした響きになってしまうためだ。また、響きの多い会場でずっと太い生音で張った音ではうるさく感じてしまう。だから音の芯は細く、まとまった音でクリアに響かせることが彼らの至上命題なのだ。だからウィーンフィルの人たちの音を近くで聴いても太い音とか大きい音だと感じることはなかった。
音質の向上
そして最後の一つは音質の向上と維持。音のクオリティを上げ、それを一定に保つということだ。これに関しては当初その概念がわからなかった。いや、わかっていなかった。
というのも、かなり感覚的なもので明確にどうとかではないが、一度感覚的に掴めばその違いは歴然となるためだ。私も当初はなんとなく理解していたつもりだったがその後学んでいくことで本質を理解することができたのだ。
簡単に説明しよう。例えば、とても情熱的なメロディを大きい音( f)で弾いていたとする。同じメロディを繰り返す時に今度は小さい音( p)で弾くように楽譜の指示があり、音量を落とす。この時に大きい音で演奏していた時のような情熱的な音を小さい音でも同じように出せているかどうかが問題だ。大抵の場合は大きい音でできても小さい音では気が抜けたような音になってしまう。これを同じように、いや、むしろ小さい音の方が情熱が詰まっている演奏をするということが音質を維持するということだ。
言葉で説明するのは難しく、これは単なる一例だが、音質は最後まで注意された分野だった。
留学したての頃は「良い音を作って維持する」くらいにしか思っていなかった「音質」に関しての感覚は、私の演奏家としての基礎の大きな部分の一つとなる。おそらくこれはヴェルバに習わなければこんなにも考えることはなかったのではないかと思う。
習い始めてすぐに感じたのは、ヴェルバは天才肌ではなく、理論派だということ。一つ一つを細かく考え、感覚で表現するところも全て頭で考えて音を処理して表現するようなタイプだ。もちろんそれは根本的に音楽に対して激しいほどの情熱があるからだが、聴衆に届けるための技術というものをしっかりと考えている人だった。気分屋で感覚に任せて演奏してしまう自分にとってヴェルバに習うことは自分の足りない部分を埋めることに非常に適していたのだった。
次回予告 :ドイツの食事情